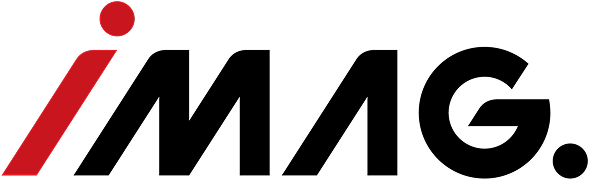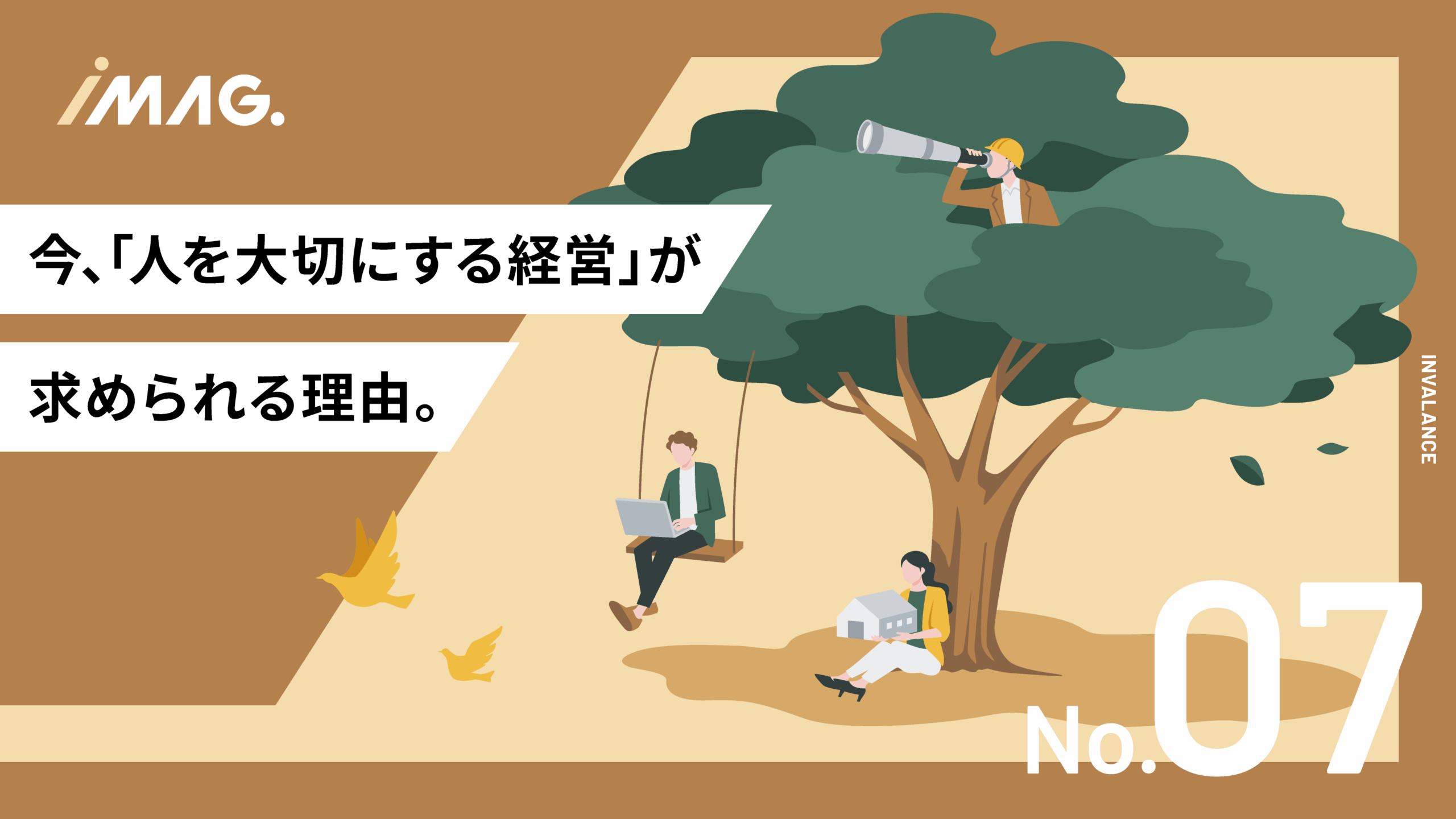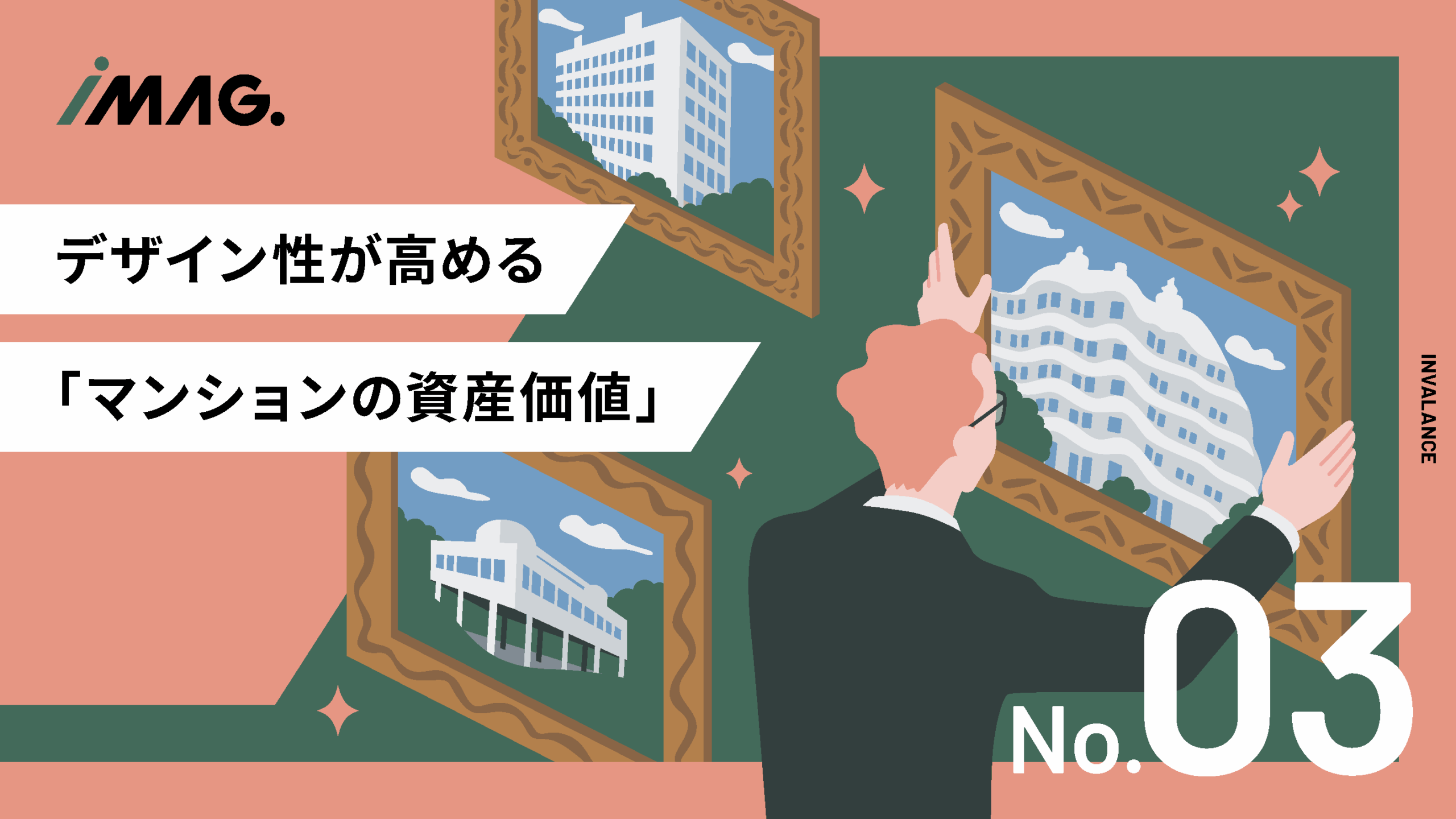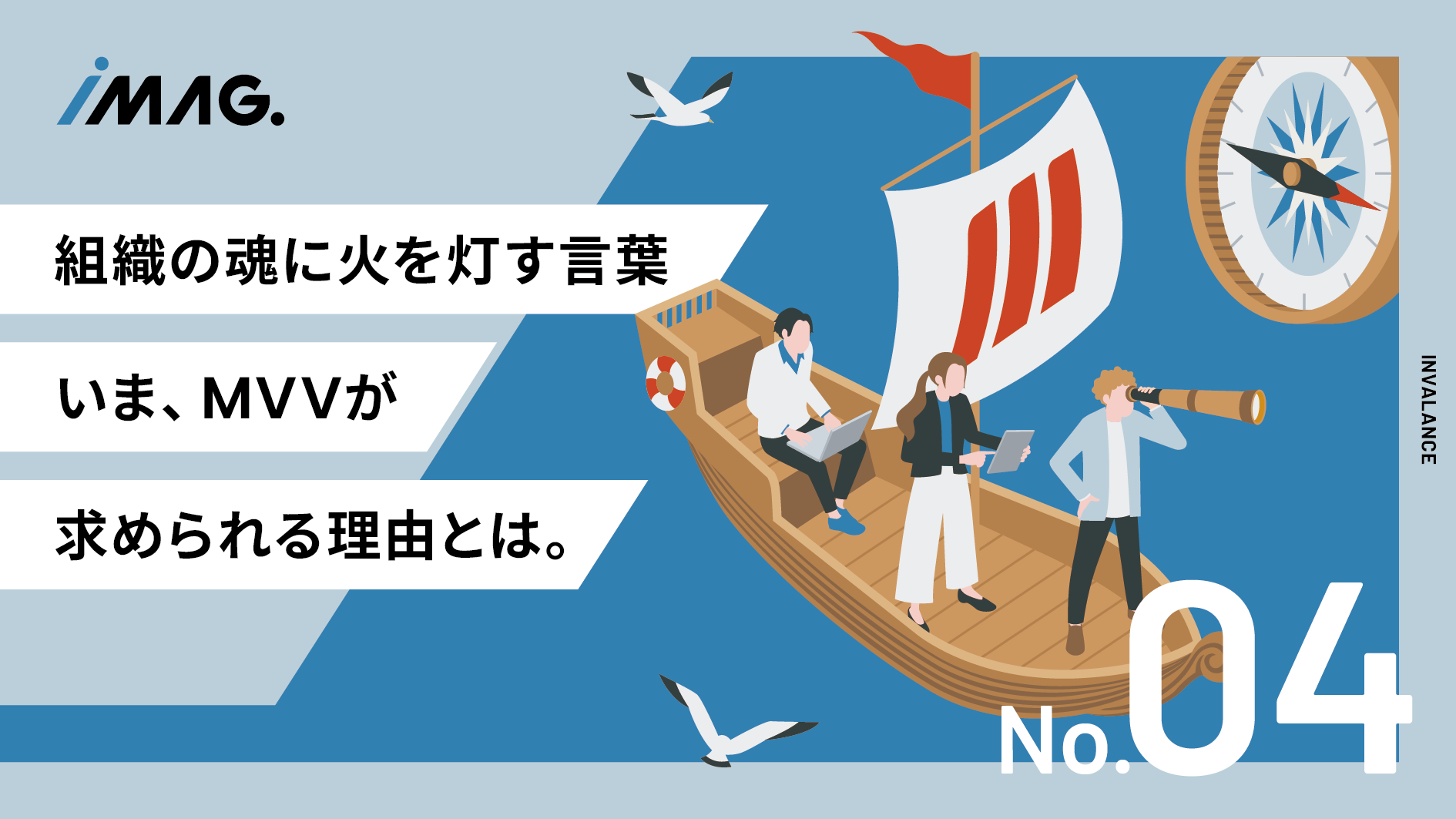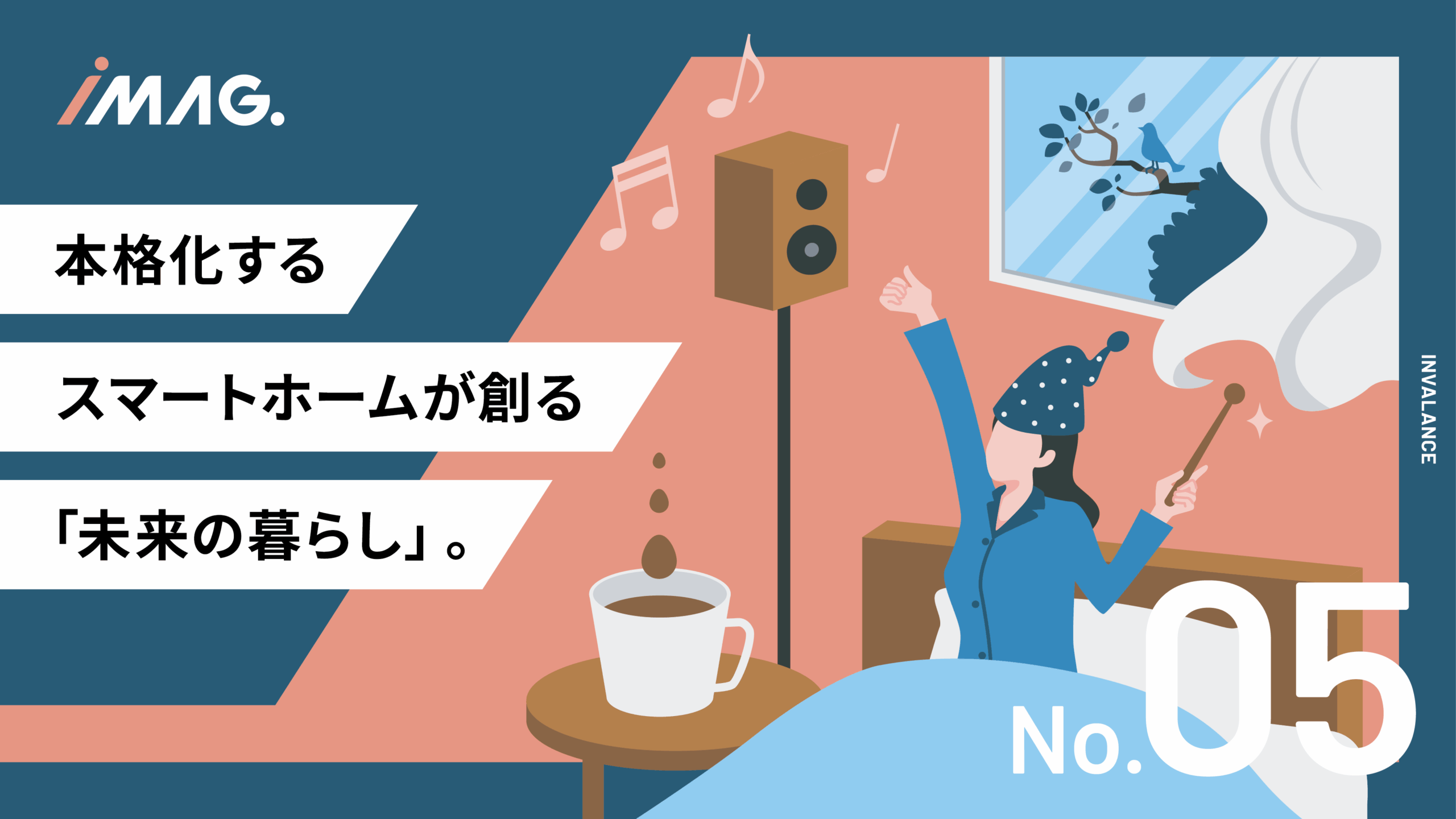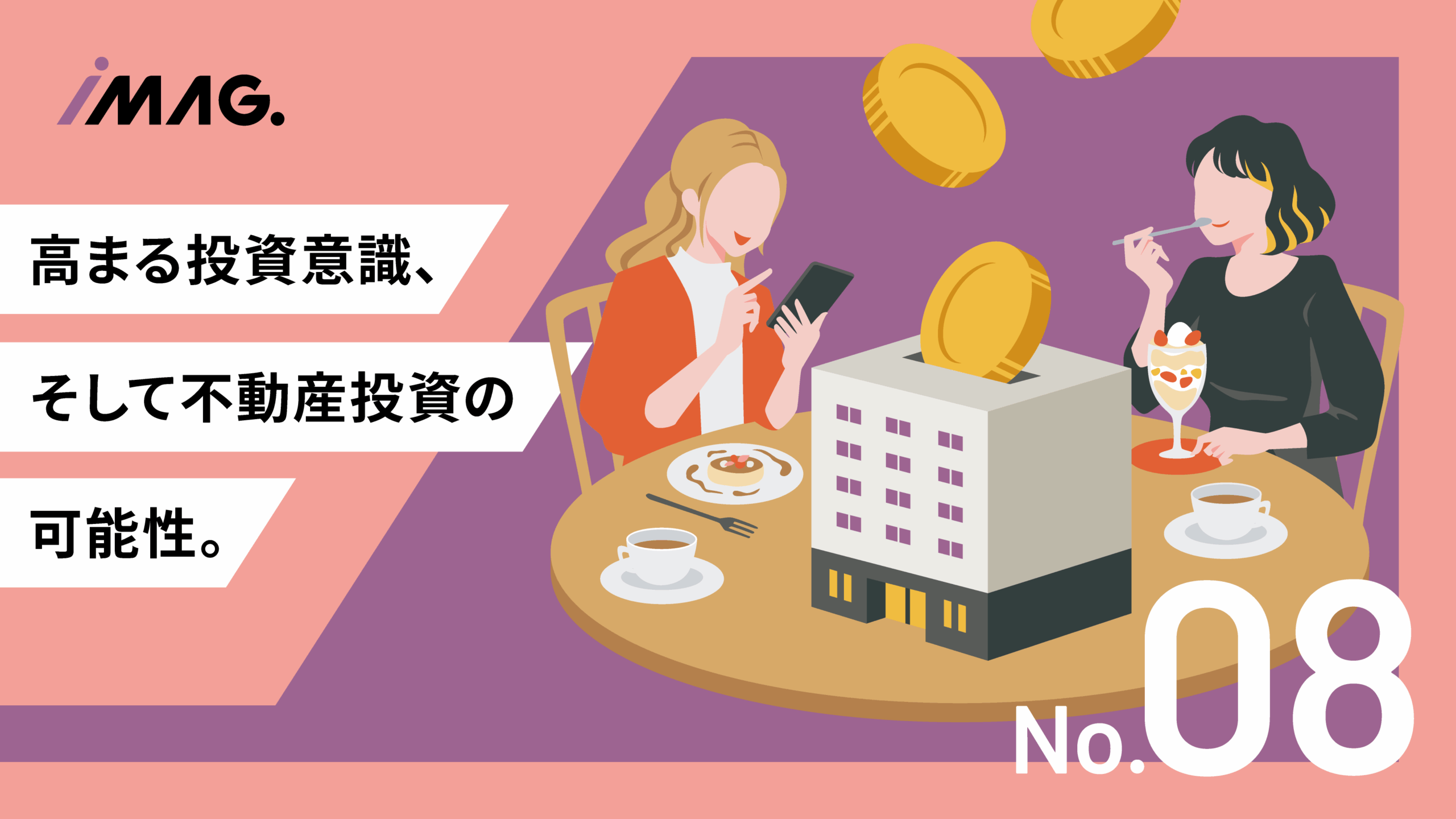これからの企業経営を支える「人的資本投資」。
人的資本投資が注目されるのはなぜ?
近年、耳にすることが多くなった「人的資本投資」という言葉。これは、「従業員一人ひとりを資本とみなし、その能力、知識、経験、モチベーションなどを高め、それを活用することで組織や企業の価値を持続的に高めていくための投資」を意味します。これまで主流だった「人的資源(Human Resources)」の考え方が「コストや配置の最適化」を重視するのに対し、「人的資本(Human Capital)」の考え方では「それぞれの従業員が持つ潜在的価値を引き出し、長期的な成果につなげること」を大切にする点で大きな違いがあります。人的資本における典型的な投資領域には、研修や教育、制度設計、働きがい、風土づくり、福利厚生、リスキリングなどが挙げられます。
「人的資本投資」が注目されるようになった背景には、社会・経済・技術などにおよぶ時代の変化があります。グローバリゼーションや情報化・デジタル化の進展により、製造業などの従来型産業における技術や資本設備だけでは差別化が厳しくなってきたことを受けて、知識やスキルといった「無形資産」の重要性に注目が集まってきたと考えられます。加えて、働き手の価値観の変化や多様性の拡大により、従業員が求める働きがいや働き方の柔軟性が企業の魅力を左右する要素として重視されるようになってきています。
ライフワークバランスという言葉が広く用いられるようになって久しいですが、これは「プライベートと仕事がお互いに影響を与え合い、好循環を生み出すこと」を指すもので、「仕事とプライベートを明確に切り分ける」「仕事を犠牲にしてプライベートを確保する」というのはやや誤った理解かもしれません。最近では、シリコンバレーのテック企業でも「996(中国のIT系企業を発祥とする働き方で、午前9時から午後9時まで週6日間働くような労働スタイルを指す)」が取り入れられていることもあると言います。企業から強要されるわけでなく、働く人個人がその働き方を望み、それが自分らしい働き方であるなら、その選択肢が用意できるのもライフワークバランスの実現のひとつとも言えるでしょう。
あわせて、法制度・開示義務の整備、投資家やステークホルダーからの期待の高まりも、人的資本投資を重視する流れの後押しとなっています。国内においては、人的資本・多様性に関する情報開示を求める法規制が強まっており、有価証券報告書などで人的資本の開示が義務化される方向で改正が進められています。海外でも、投資家が人的資本に関する定量データを投資判断に用いる動きが強まっており、企業の透明性を高めることが競争力の一端として見逃せないものになっているのです。
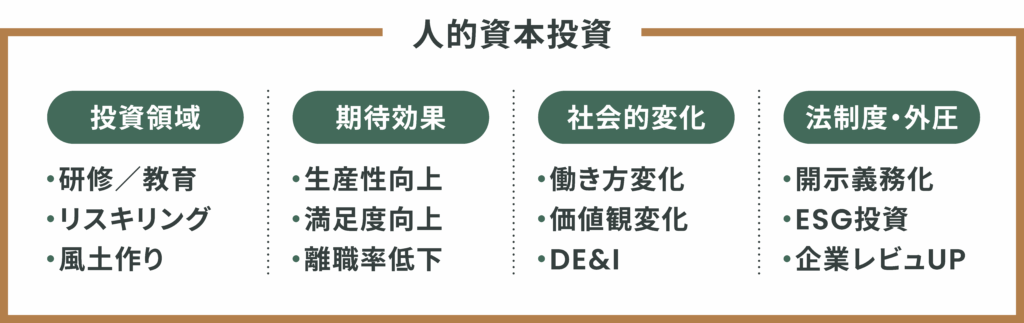
人的資本投資が重視される具体的要因4選
「人的資本投資が重要」と企業や経営者に認識されるようになった要因を、具体的に整理すると以下のようなものがあります。
❶ 変化の激しい市場環境と技術革新
デジタル化、グローバル競争、AI や自動化などテクノロジーの進展により、スキルの陳腐化が加速しています。短期的な固定資産や設備投資のみでは対応できない変化が増えており、従業員の継続的な学習、リスキリング、柔軟な能力開発が競争力の源泉になっています。さらに、イノベーションを生み出す組織文化や、知識共有・創造性を促す環境整備の推進が重視されるようになっています。
❷ 投資家・ステークホルダーからの圧力と期待の高まり
ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大がその代表例。ESG のうち、「Social(社会)」に関連する要素として、人的資本への配慮や働き手のケア、健康や多様性の確保などが企業評価のひとつになっています。投資家は企業に対して、人的資本に関する成果をいかに示すのかを注視しており、企業側もその取り組みを強化し、的確に開示することが求められているのです。
❸ 法制度・開示義務および企業評価の可視化
日本においては、内閣官房が非財務情報可視化研究会を設置し、人的資本可視化の指針を公表しています。また、金融庁やその他監督当局が人的資本・多様性に関する開示義務の強化を進めています。このような制度改正により、企業にとっては「人的資本への投資をするだけでなく、その成果を測定・報告すること」が求められるという環境が整備されつつあり、投資の意義を明確にしようという動きが促されています。
❹ 経営の持続性・企業価値向上への期待
人的資本投資が従業員に及ぼす影響は、より一層、関心を集めています。組織で働く人のモチベーションやロイヤリティを高め、生産性を向上し、ひいては離職率の低下につながる。それが経営の安定性を強め、中長期的なコスト削減と利益拡大に貢献する。人的資本への投資にはこうした期待が込められています。人的資本を重視した経営は、組織の柔軟性や創造性を強化し、技術や競争環境の急激な変化をはじめとする予期せぬ外的ショックにも対応しやすくなるというメリットがあります。
人的資本投資がもたらす企業と社会への影響
人的資本投資を重視した経営が広まるにつれて、企業はもちろん、社会にもさまざまなポジティブな影響が現れてきています。
企業側では、人的資本投資の成果が徐々に可視化されるようになってきました。研修や教育投資が財務成果と結びつく実証研究が増加しており、「社員育成=経費」ではなく「将来的なリターン」を生む投資であるという認識が高まっています。また、優秀な人材の採用や定着が進み、社員満足度やエンゲージメントが向上することで、組織文化が強化され、生産性や創造性が高まる例が増えています。社会的には、「多様性(Diversity:ダイバーシティ)」「公平性(Equity:エクイティ)」「包摂性(Inclusion:インクルージョン)」といういわゆるDE&Iや働き方の柔軟性が拡大することで、質と量の両面において労働市場全体が改善し、持続可能な成長や社会を支えることが期待されています。こうした動きは、政府・監督機関・生活者の支持も得やすく、企業のレピュテーションにも好影響を与えることでしょう。
一方で、乗り越えるべきハードルもあります。ここでは四つの課題を挙げて考えてみましょう。一つ目に、「投資対効果の可視化」が十分でないことが挙げられます。多くの企業が、人的資本投資に関連する個々の施策がどれだけの成果をもたらしたかを定量的に測定・評価できておらず、その効果を正確に把握できないという声があります。二つ目は、人的資本戦略と経営戦略の連動が弱い企業がまだまだ多いこと。制度設計、育成プログラム、働き方制度といった施策が、経営の方向性や将来ビジョンと整合していないケースがあり、部分最適で終わってしまうことが少なくありません。三つ目が、時間・費用・人的なリソースやノウハウの不足という障壁です。特に中小企業などでは、人的資本投資への意欲は高いものの、予算や育成の仕組み、データ計測手法などが整っていないため、最初の一歩が踏み出せないケースが見受けられます。そして最後の四つ目が、外部環境への対応。VUCAの時代はあらゆる事象の変動が予想以上に速いため、過去の枠組みへの過度な依存は急激な陳腐化を招くリスクをはらんでいます。
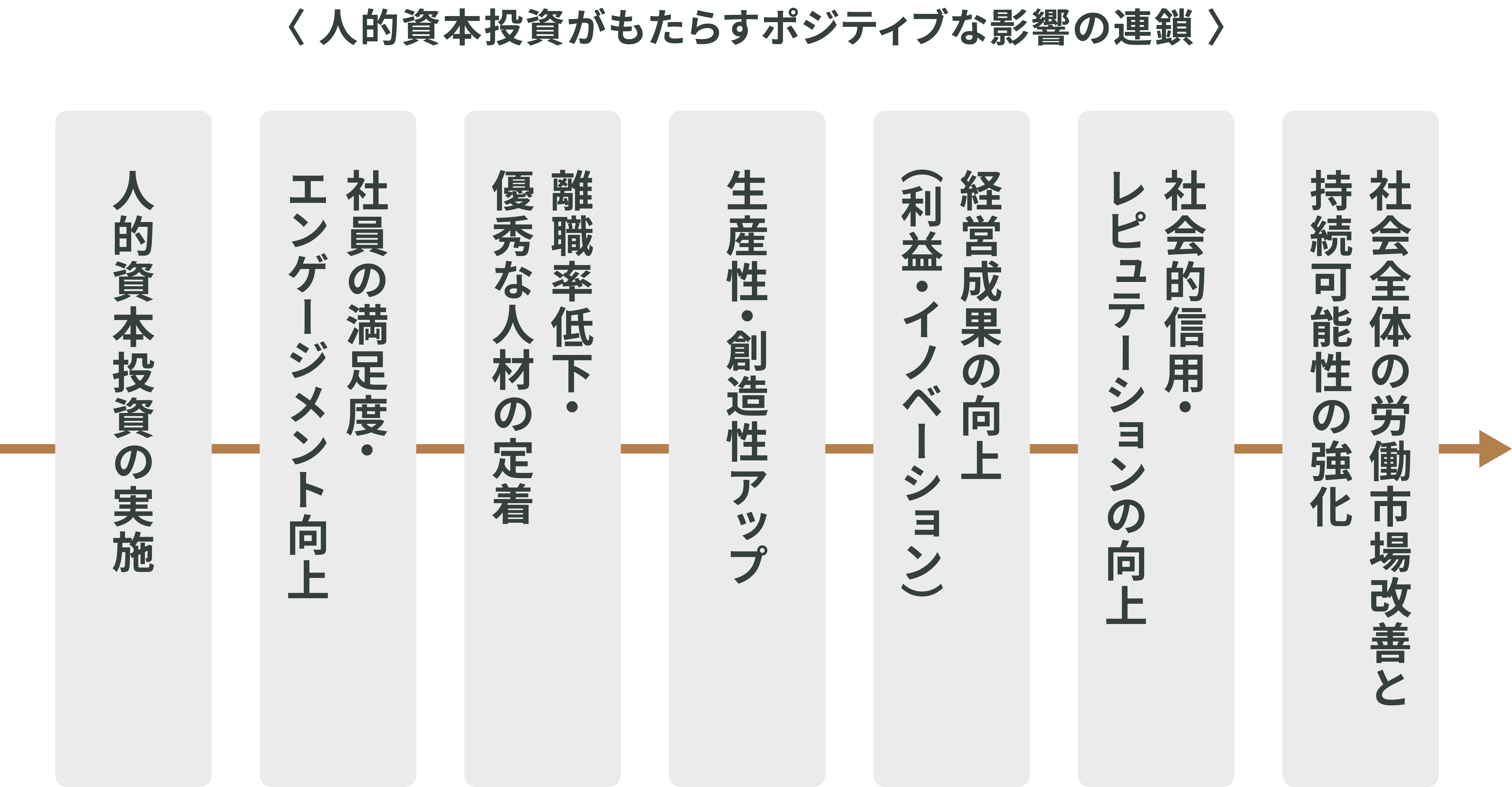
人的資本投資が機能するために
こうした課題を乗り越え、人的資本投資を真に重視するためには、いくつかの方向性が考えられます。
❶ 投資した施策ごとに KPI を設定し、定量的に成果を追う。教育・研修だけでなく離職率、従業員満足度、能力開発の速度や適用度などをモニタリングすること。
❷ 経営トップ・経営陣が人的資本投資を経営戦略の中核に位置づけ、組織横断で施策を設計・推進すること。
❸ 多様性・インクルーシブネス、働き方の柔軟性など、従業員の多様なニーズに応える制度を整備すること。
❹ データ基盤の整備。人的資本の可視化(定性・定量両面)を強化し、ステークホルダーに対して透明性を持って説明できるようにすること。
人的資本投資が重視されるようになったのは、企業を取り巻く環境が大きく変わったこと、法制度や投資家の期待が変わったこと、そして、人的資本への投資が経営の持続性や価値向上に直結すると認識されるようになったことが背景にあります。今後は人的資本投資の成果をどれだけ可視化できるか、戦略との整合性を保てるか、企業全体で活用できる仕組みづくりが鍵となるでしょう。