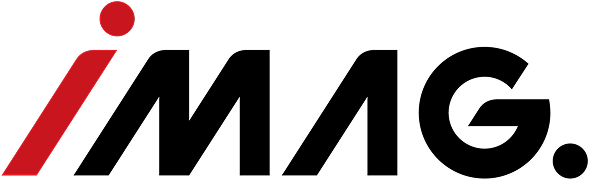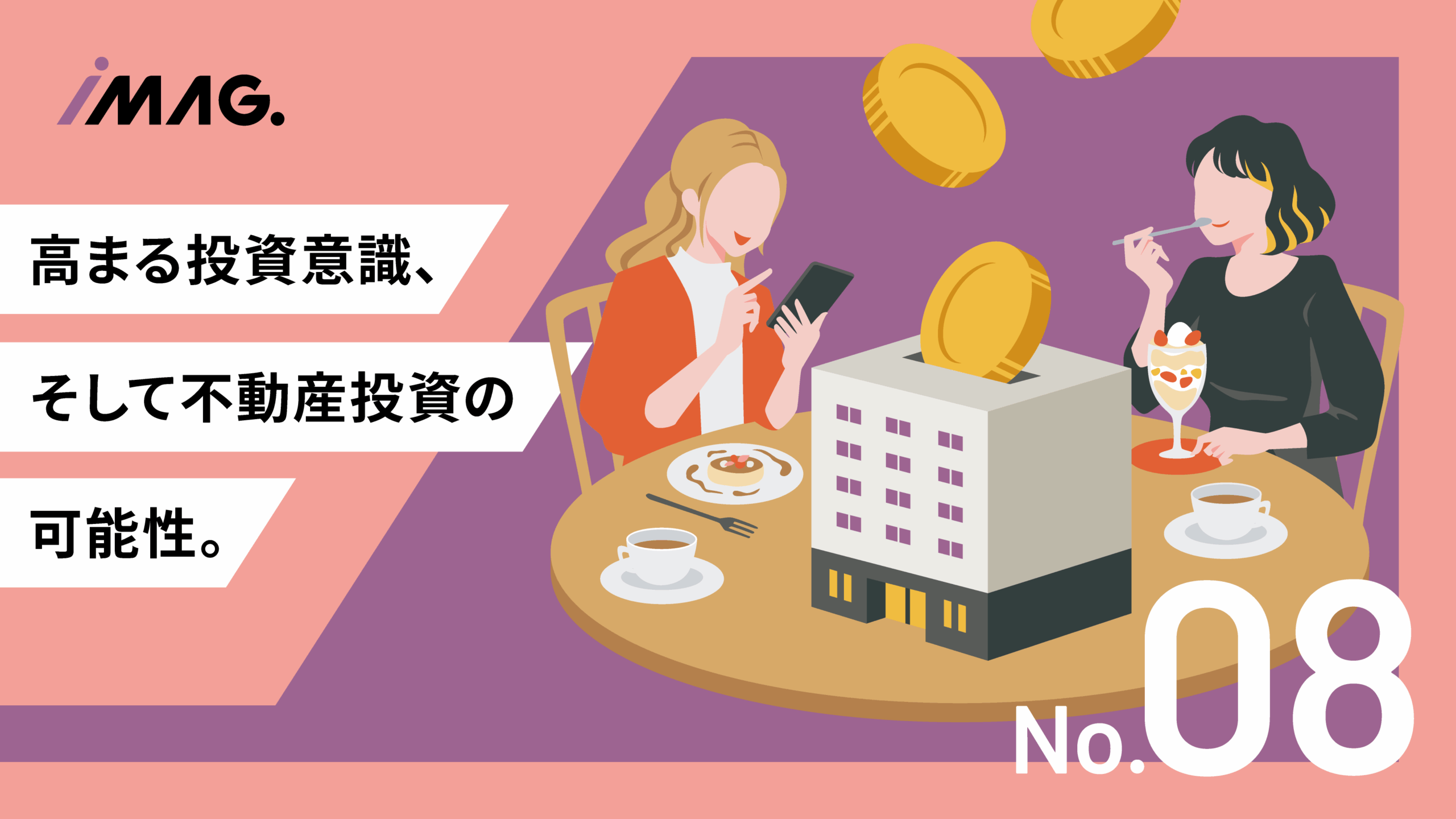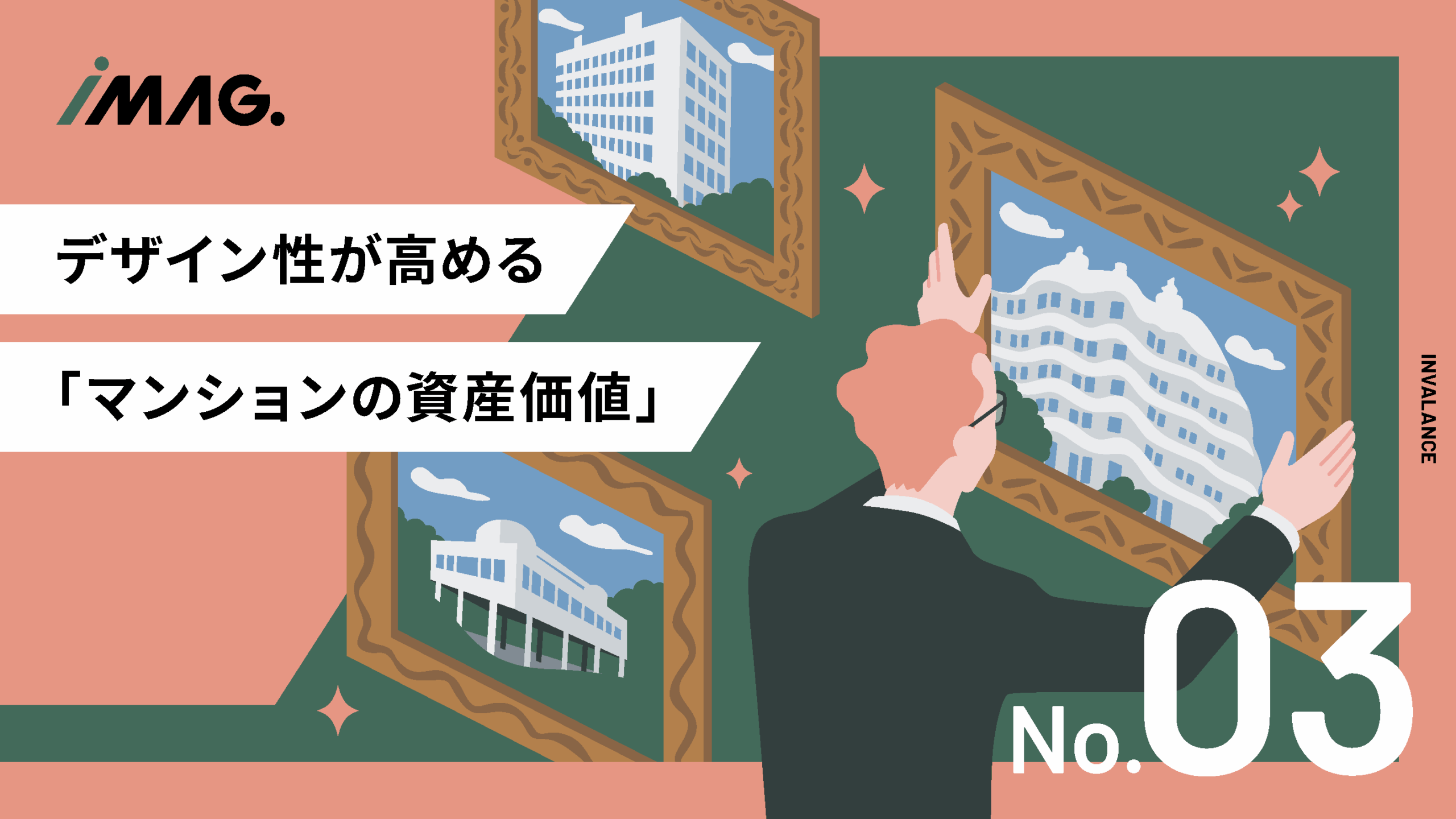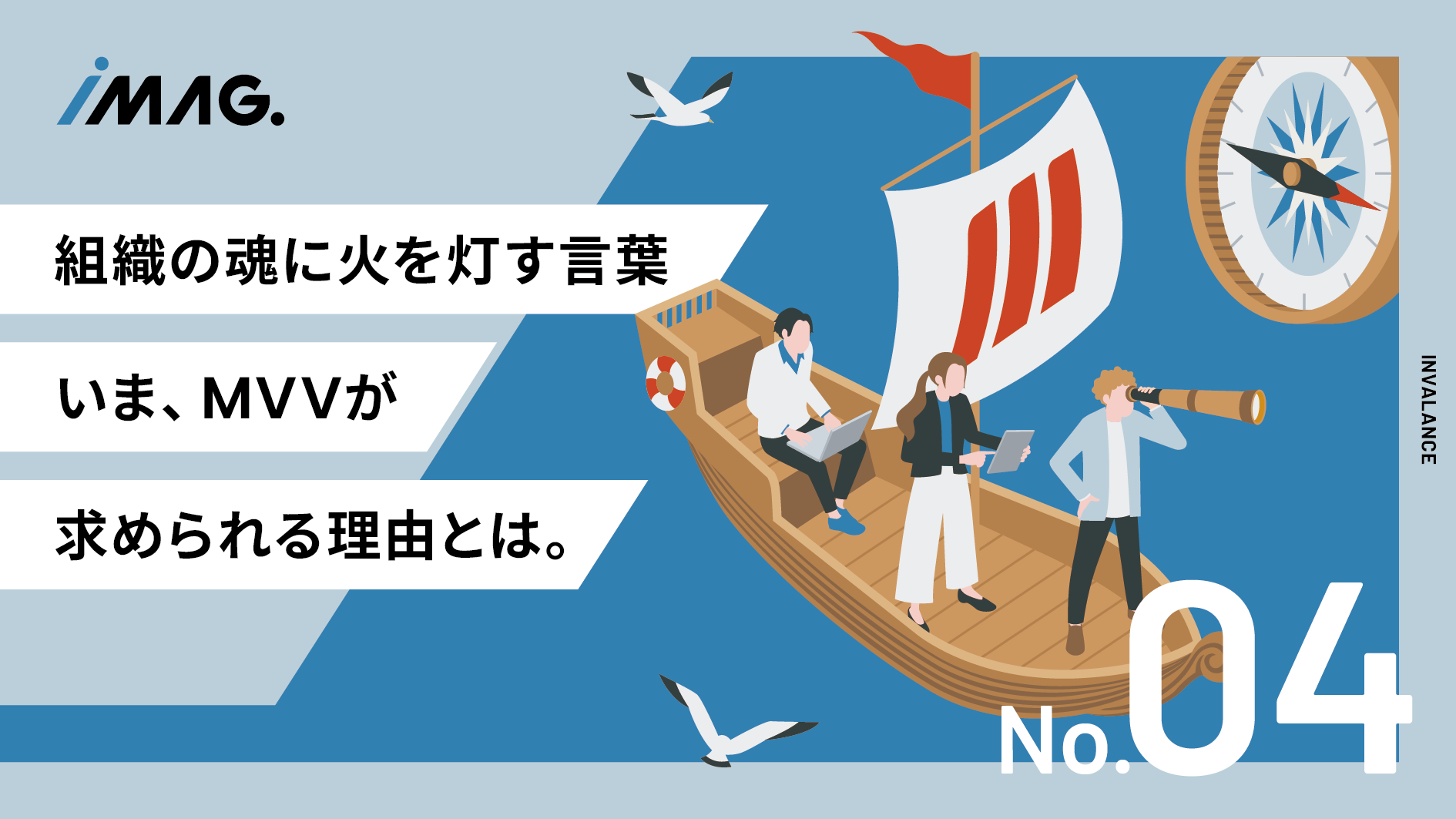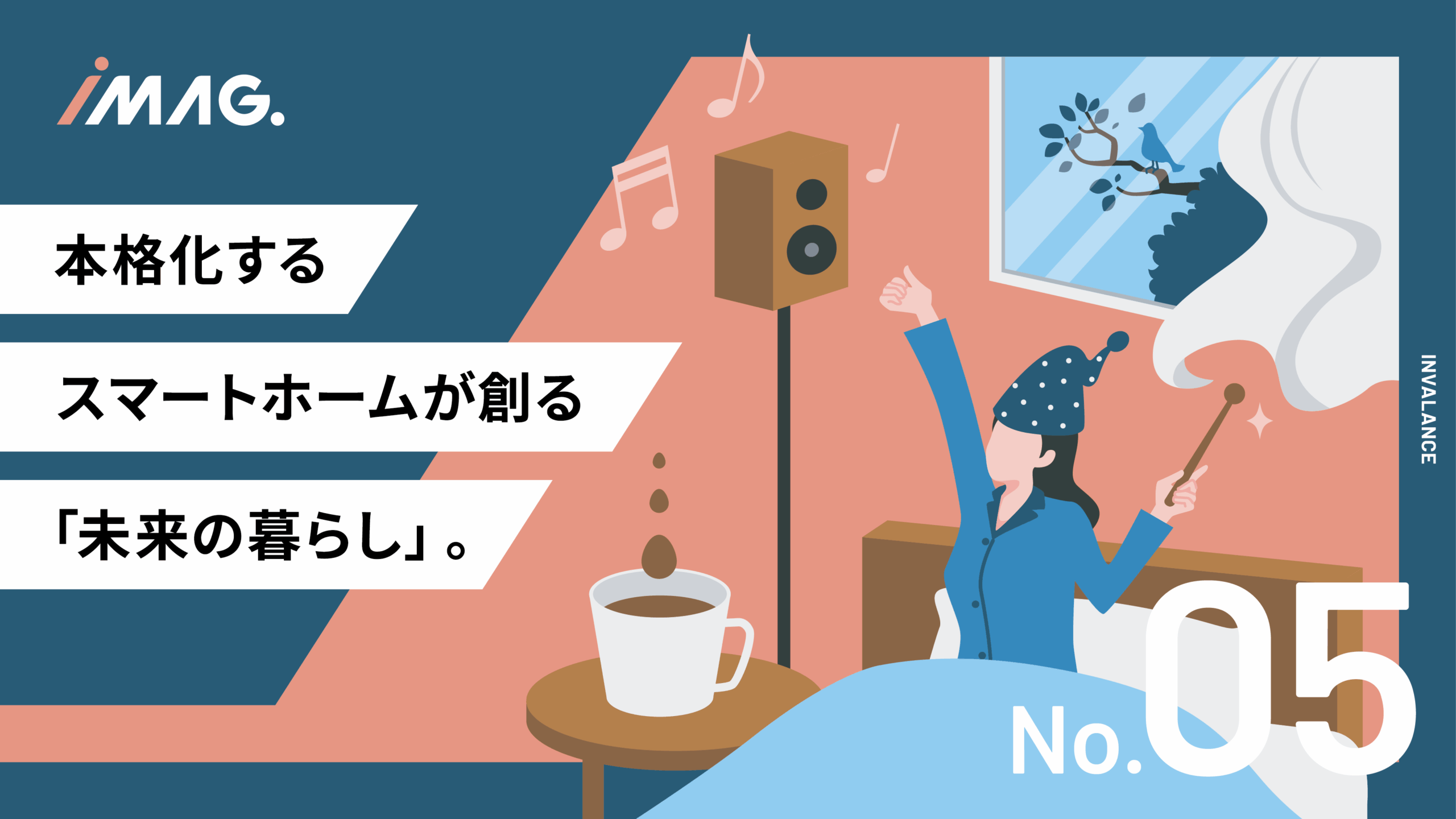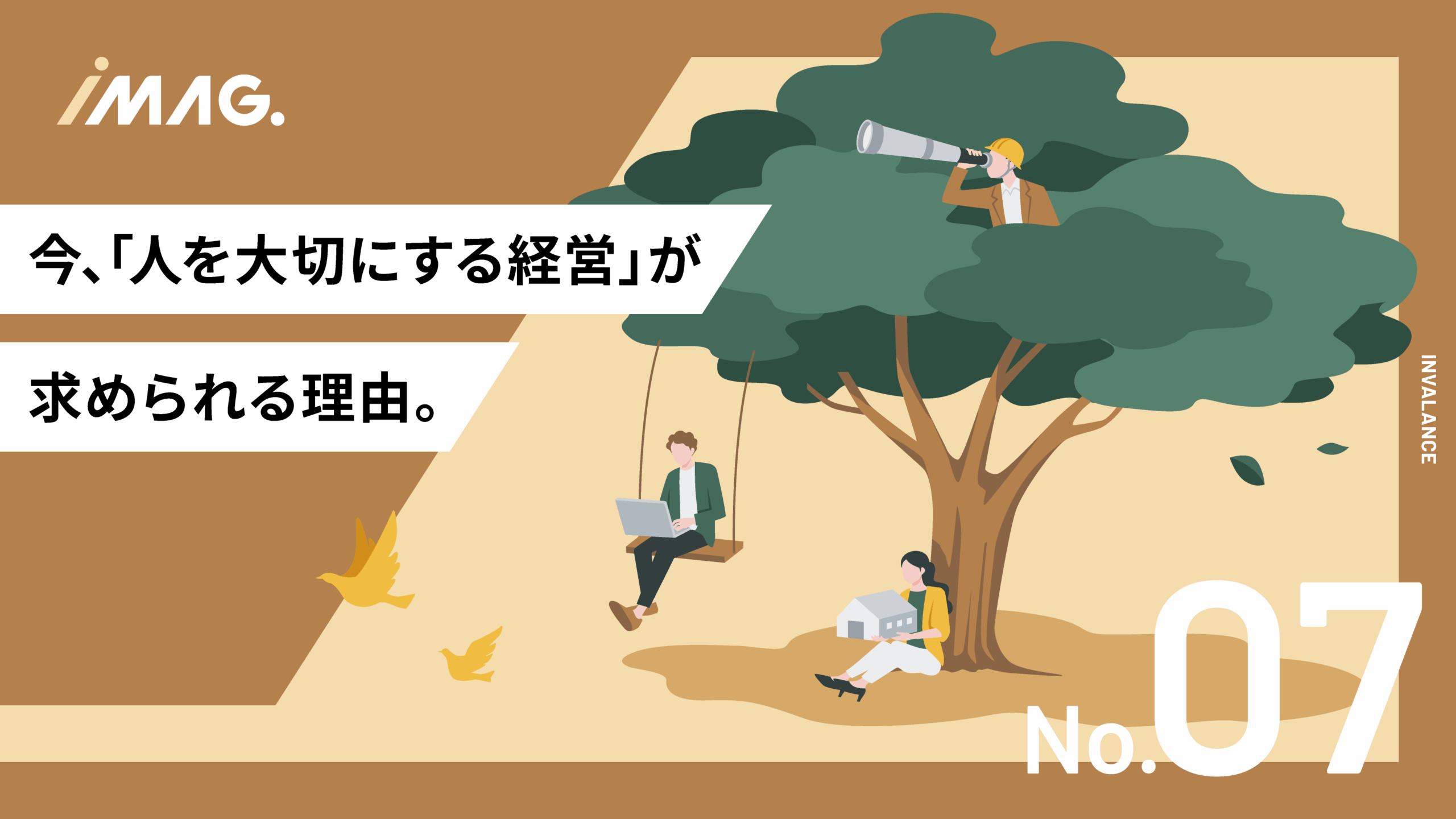人生100年時代に考えるべき「投資との付き合い方」。
投資をしないことがリスクになる時代。
2024年の「新NISA(少額投資非課税制度)」のスタートを機に、日本は今、かつてない投資ブームの渦中にあると言われています。実際、皆さんの周りにも個別株や投資信託などの株式投資、金やプラチナなどの現物資産投資、あるいは不動産投資など、さまざまな資産への投資を始めている方もいらっしゃることでしょう。一方で、それと同じくらい、もしかするとそれ以上に「自分は投資とは無縁だ」という人がいるのも確かなところで、実態はよくわかっていないというのが正直なところではないでしょうか。果たして、この投資ブームは一体どれほどのものなのか。日本人の投資意識を振り返りながら紐解いて行きたいと思います。
日本では長年にわたり、「貯蓄」を重んじる文化が主流でした。そこには「高金利時代の記憶」が少なからず影響を与えていると考えられます。1980年代前半は、定期預金金利が7%という、現在の超低金利時代からは想像もつかないような時代でした。100万円を預けておけば1年で7万円の利息が付くわけですから、株式投資や不動産投資といったリスクの高い投資にわざわざ手を出す必要がなかったとも言えるでしょう。「銀行に預けておけば安心」といった感覚は、当時の世の中の空気を知る人にこそ多いものかもしれません。
しかしながら、これからの時代は、銀行預金で資産を保有しているだけではリスクがあると言わざるを得ません。主な理由として次の三点が挙げられます。
❶ インフレ圧力の高まり : まずはインフレ、すなわち物価上昇圧力です。物価が上がると、現金の価値は相対的に目減りします。物価が上昇すれば、同じ1万円で買えるものが少なくなるのです。預金金利がほぼゼロに近い現状では、現状で約2%程度と言われているインフレ率を下回っており、実質的に資産を減らす可能性があるのです。これは、将来的な購買力を維持するうえで深刻な課題となります。
❷ 高齢化社会の進行と公的年金制度の限界 : 日本の平均寿命はますます延び、「老後」と呼ばれる期間が長期化しています。リンダ・グラットンとアンドリュー・スコットの共著書『LIFE SHIFT』を契機に、「人生100年時代」という表現が広く知られるようになりましたが、この言葉は単に長寿社会を意味するだけでなく、働き方・学び方・資産形成のあり方そのものが大きく変化することを示唆しています。退職後も20年、30年と生活を続けることが当然となりつつある一方で、公的年金制度は支給開始年齢や支給水準を見直さざるを得ない状況にあり、将来の年金支給額は必ずしも十分とは言えない可能性が高くなっています。いわゆる「老後2,000万円問題」も、この文脈から生まれたものです。老後資金を年金だけに依存するのはリスクであり、自分のための資金は自分で賄うという考え方をインストールする必要があるのです。
❸ 社会保障費増大と国家・地方財政の圧力 : 人口減少や高齢化に伴い、医療・介護・年金などの給付に必要な予算は膨張します。国としては給付抑制や自己負担増などで対応せざるを得ず、国民に対してさらなる自助努力が求められる時代がすでに到来しています。
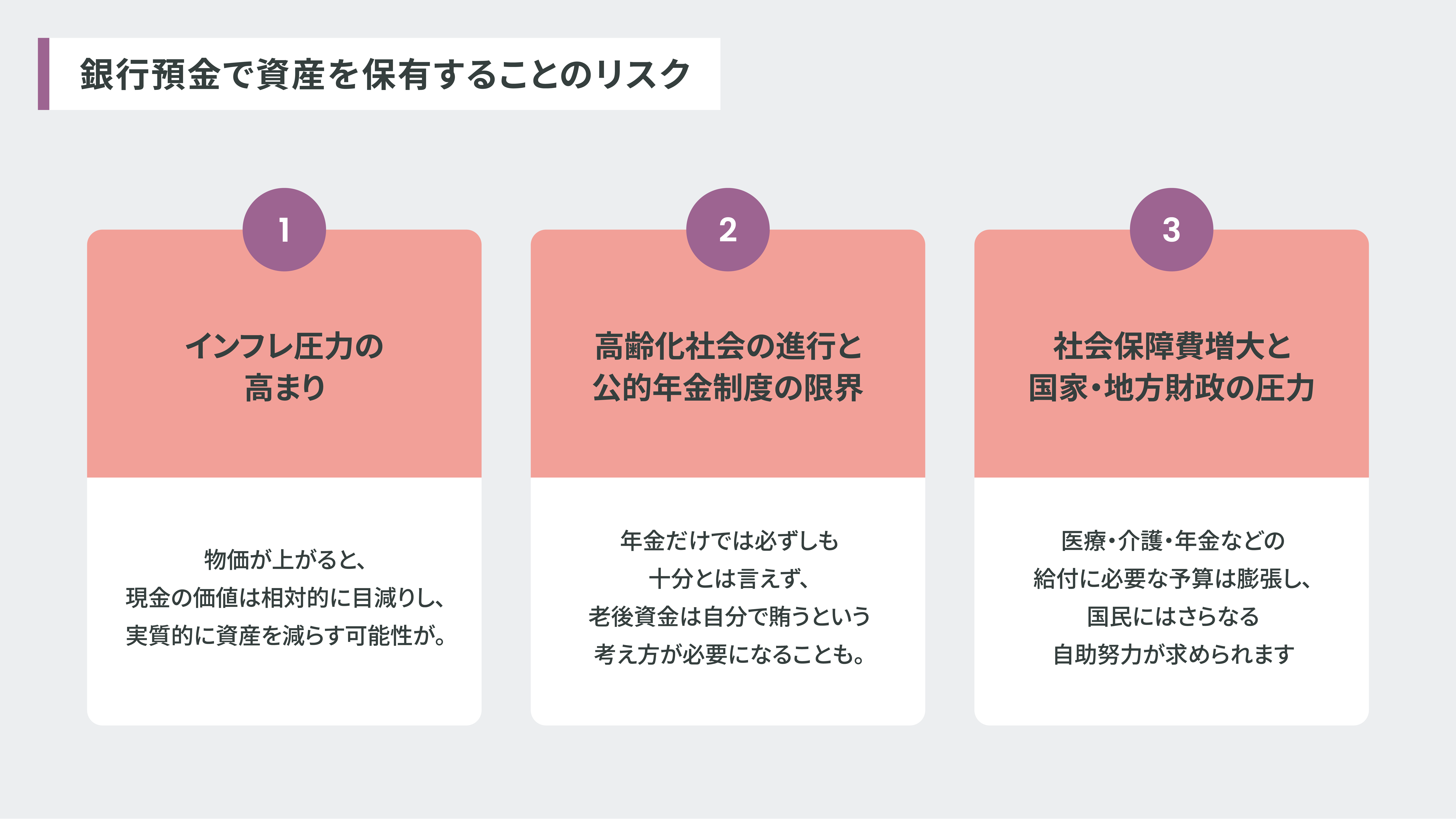
「資産、特に現金の実質価値が目減りする可能性があること」「老後の備えが不足する恐れがあること」「将来的な経済変動(為替・利率・税制など)への耐性が下がる可能性があること」から総合的に判断すると、今、この時に投資を行わないのは、見えないリスクを引き受けることになると考えて良いでしょう。
日本人の投資の実態 — 未だ少数派に留まる個人投資。
日本では現状、投資を行っている人はまだ少数派に留まっています。2021年の日本証券業協会による調査では、「何らかの有価証券を保有している人」の割合は約19.6%で、それ以前の水準と比べても大きな飛躍は見られませんでした。それに対し、世帯ベースではありますが、米国では「株式を保有している世帯」は52.7%(2019年)、「投資信託を保有している世帯」は46.0%(2020年)で、日本の2倍以上となっています。また、2025年の日本銀行調査統計局の調査を見ると、国内金融機関の資産構成における個人資産配分では「現金・預金」が大きな割合を占めており、株式や投資信託といったリスク資産の比率は非常に低く抑えられているというデータも見られます。この傾向は先進国のなかでも非常に特徴的とされています。一方、最近では投資への興味を抱く人は増え始めています。MMD研究所の調査によれば、20~69歳を対象にした調査で「投資に興味がある」と回答した割合は45.7%。そのうち、「既に投資を始めている」と回答したのは22.8%で、「興味を持っている人」と「実際に投資をしている人」との間に大きなギャップがあることがうかがえます。
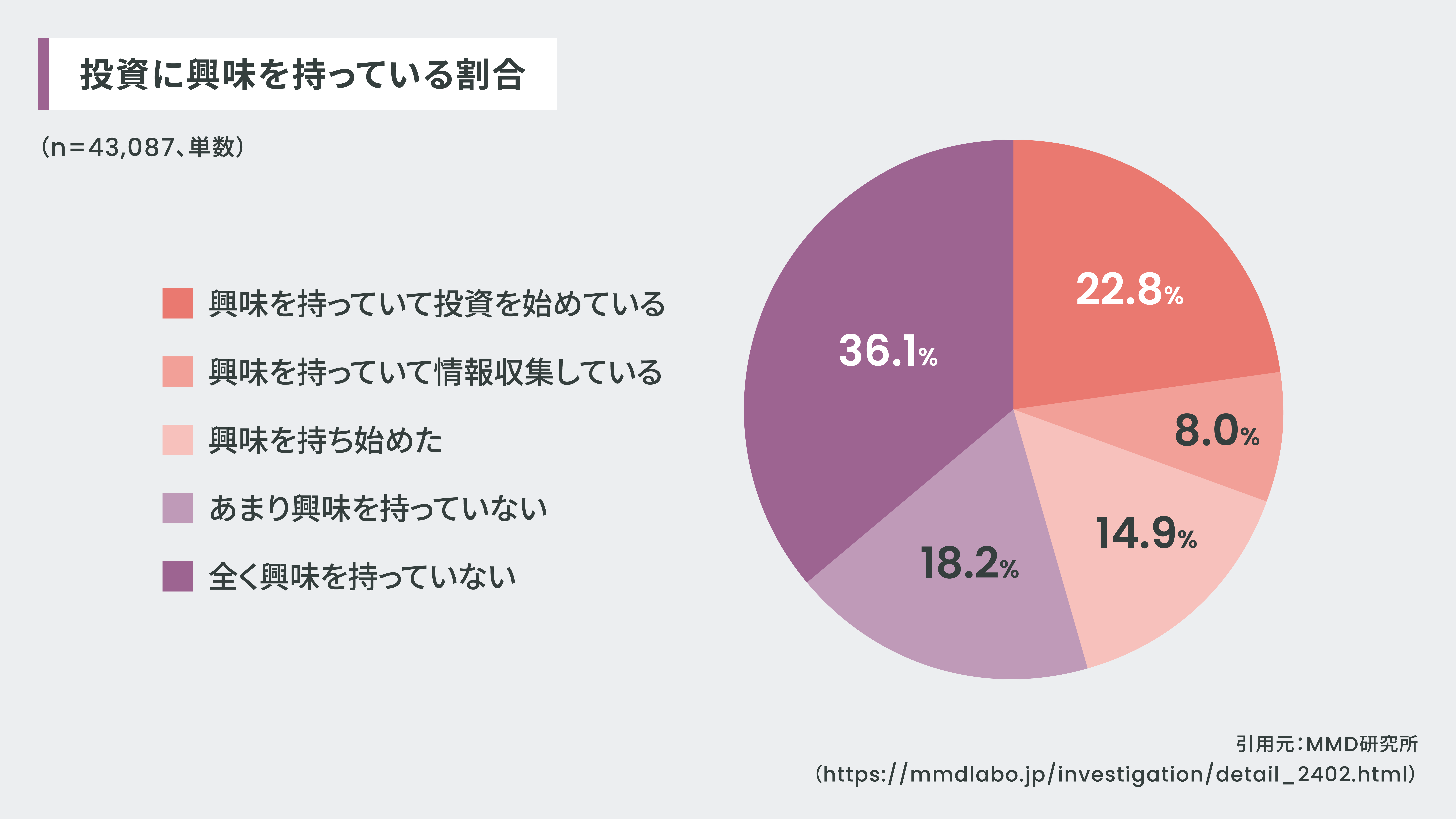
近年の投資機運を後押しする制度として、2024年から始まった「新NISA(少額投資非課税制度)」が挙げられます。これは「日本国民の投資しやすさ」を重視した税制優遇制度であり、多くの期待が寄せられています。新NISA開始から1年が経過した段階での日本証券業協会の調査では、「2024年内に新NISAで金融商品を購入した人」のうち、「つみたて投資枠の利用者」は約78.9%(平均購入金額:約 47.3 万円)、「成長投資枠の利用者」は約71.1%(平均購入金額:103.3万円)という結果が出ています。また、金融庁によると2025年3月末時点での新NISA口座数は約2,647万口座、総買付額は59兆円にまで達していますが、これを日本の家計金融資産と比較すると、預金・現金の総額に対しては約5%程度に留まっています。18歳以上の人口ベースで見ると新NISA口座保有率は約24.8%、現役世代(18〜64歳)では37.5%という数字も報告されていますが、実際の稼働率となると7割程度と考えられています。NISA口座開設数だけでは日本人の投資の実態は見えてこないことには注意が必要かもしれません。
若年層にこそ投資に関心を持ってほしい、これだけの理由。
年代別で見ていくことで新しい傾向も見えてきます。日本証券業協会による「個人投資家の証券投資に関する意識調査(2024年)」によると、有価証券保有者を対象にした調査で「新NISA口座を開設している」人の割合は59.3%。興味深いことに、20代・30代ではこの割合が76.9%と非常に高い水準にありました。また、若年層の開設率増加の傾向は金融庁の調査でも認められており、29歳以下の口座開設率は前年17.0%から24.5%に上昇しています。
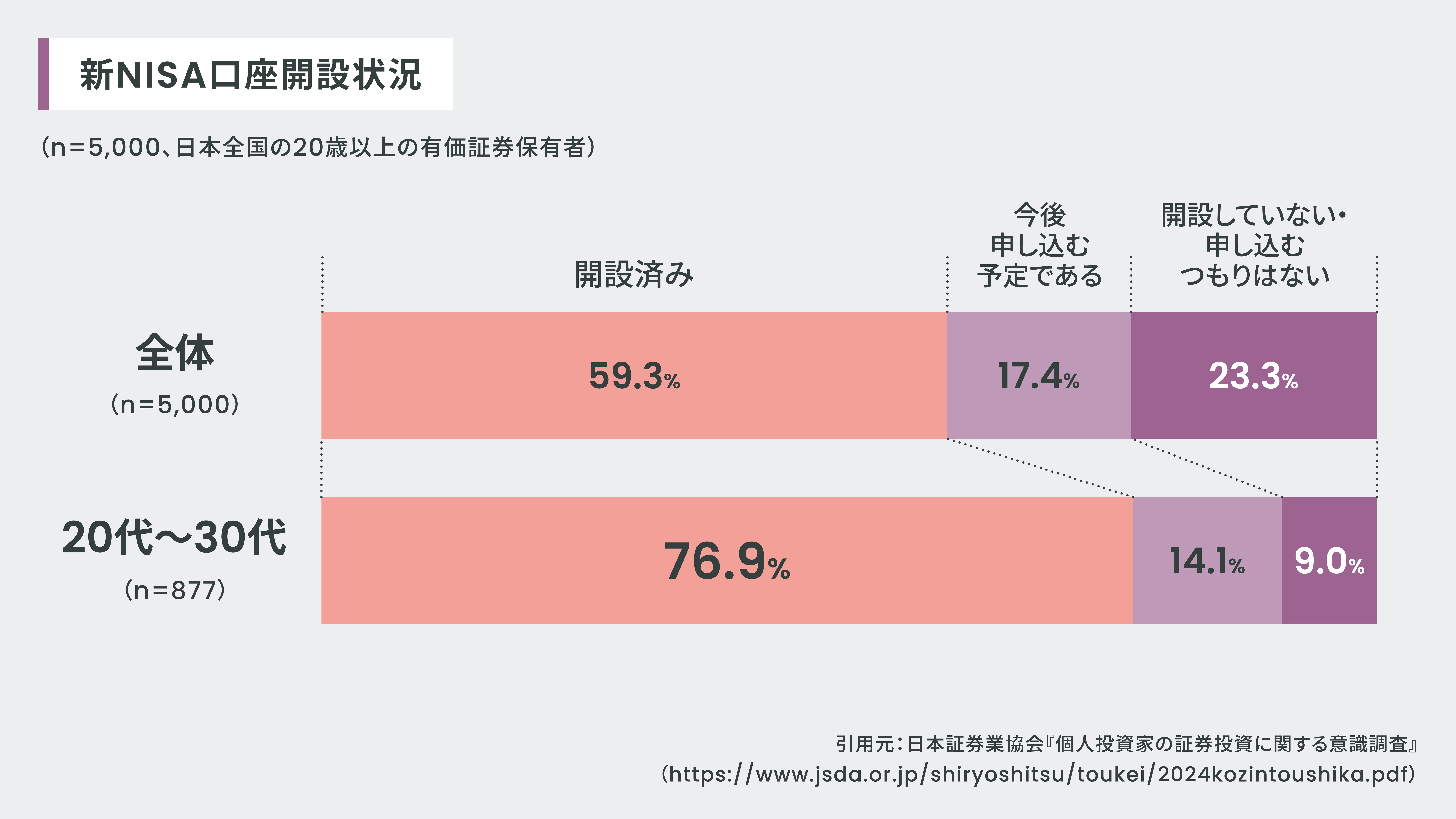
「投資はある程度の資金を持ってから始めるもの」という一般的な認識があるなかで、近年では若い世代の間で投資への関心が確実に高まりつつあることがわかるでしょう。若年層は、想像以上に投資に対する興味を持っているのです。
早くから投資を始めることには、以下のような明確なメリットがあります。
❶ 時間を味方にできる(複利効果の活用) : 投資の最大の武器、それは「時間」です。たとえば、毎月定額を長期にわたって継続して投資することで「複利効果(利益がさらに利益を生む構造)」が機能します。40年、50年と長期で運用することで、若いうちの積立が将来において大きな差と生むことになるのです。
❷ リスク許容度の柔軟性 : 若い世代は扶養家族も少ないことが多く、その分だけ資金的にも心理的余裕があり、相場の変動に対する耐性も持ちやすいと言えるでしょう。資金的余裕があれば、多少の変動があっても投資に対する態度も影響を受けにくくなります。
❸ 投資経験・学習期間の確保 : 早くから始めることで、市場の動きや投資手法、リスク管理などについて、実体験を通じて学ぶことができます。若いうちであればリカバリーも効き、試行錯誤を許容できる期間を長く取ることができます。
❹ 将来設計の幅が広がる : 資産形成が早く進めば、住宅購入、起業・副業、海外移住などを含め、ライフプランに柔軟性が生まれます。貯蓄だけでは難しい選択肢にも、積極的に踏み込む余裕を持つことができるかもしれません。
❺ インフレや将来リスクへの備え : 物価上昇や公的制度の変化に対応するには、資産運用が一つの防衛策となります。若いうちから準備しておくことで、将来の不確実性を軽くできます。
20代以下の若い世代は、社会保障や年金制度が将来十分に機能しないかもしれないという現実を直感的に理解しています。だからこそ、「自分の将来は自分で準備する」という意識が芽生えやすく、こうした若年層の投資への前向きな姿勢は、日本全体の投資志向や資産形成文化を大きく変えていく可能性を秘めています。今後、さらに金融教育が充実し、投資環境の改善が進むことで「21世紀を生きるものとして投資は当然の行動」「投資はひとつのライフスタイル」という認識が根付いていくことでしょう。
若年層に限らず、投資は始めてみなければわからないことも多いもの。自分自身が許容できるリスクの範囲内でとにかく投資の第一歩を踏み出し、少しずつ知識と経験を積むことで、自分にあった投資スタイルを確立していけば良いのです。必要以上に恐れることなく、わからないことはありつつも、まずは始めてみる。その姿勢が一人ひとりの未来を作っていくに違いありません。